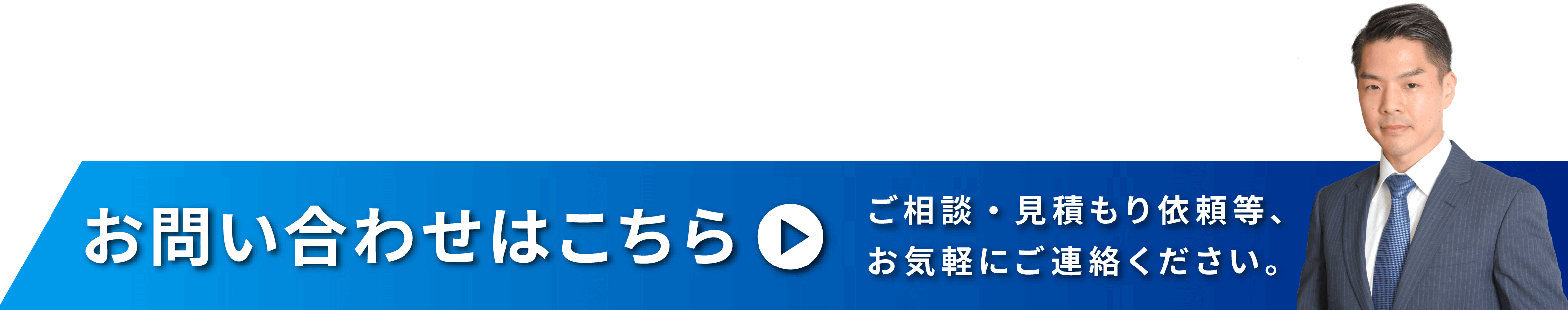同一法人が同一州又は複数州に拠点や支店を持っている場合に、複数のGST番号を有しているケースがあります。例えば、ハリヤーナ州に本店がある一方で、カルナータカ州に倉庫を有しており両州でGST番号を取得済みの場合です。このように、同一法人が同一州内また複数州内に2つ以上のGST番号を取得している者をGST法では「Distinct persons」と呼びます(CGST法第25条4項)。なお、似て非なる概念として「Establishments of Distinct persons」もGST法では規定されていますが(IGST法第8条 Explanationの1)、詳細はこちらをご参照ください。
Distinct persons間での取引価格の決定方法
Distinct persons間で物品又はサービスの供給を行う際は、同一法人間内での取引のため市場原理が働かず、取引価格を当法人の思うままに決定することができてしまいます。そこで、CGST法細則第28条はDistinct persons間で物品又はサービスの提供を行う際は公開市場価格(Open Market)で取引価格を決定するよう求めています。公開市場価格(Open Market)とは、資本関係のない法人間で評価対象となる供給が行われた時点で、当該供給を得るために人が支払うべき、GST法に基づく租税を除いた金銭の全価値をいいます。
また、公開市場価格(Open Market)が入手できない場合には、同種・同品質の物品又はサービスの供給価格を用います。その価格の取得も難しい場合は取得価格の110%を取引価格とする方法(CGST法細則第30条)や残存価格法(Residual method)(CGST法細則第31条)を用いて、取引価格を決定します。
なお、Distinct persons間で物品の供給の際に、受領側が当物品をさらに他の者に供給することが意図されている場合には、関連者でない顧客に対して、同種・同品質の商品を提供する際に請求する価格の90%に相当する金額をDistinct persons間の取引価格とすることもできます。
一方で、受領者側が全額の仕入税額控除を使用できる場合、請求書に記載されたサービス供給の金額が公開市場価格(Open Market)とみなされます。受領側が全額の仕入税額控除を使用できない場合とは、受領者がExempt supplyを供給する場合やDistinct persons間の仕入れ(Inward Supply)に係る仮払GST(Input GST)がBlocked Creditに該当する場合等です。
また、間接税・関税中央委員会(Central Board of Indirect Taxes and Customs - CBIC)は2023年7月17日付で通達Circular No. 199/11/2023-GSTを発し、受領者側が全額の仕入税額控除を使用できる場合で供給側が請求書を発行していないサービス供給に関しては、公開市場価格(Open Market)はNilとみなされると明確化しました。
受領側が全額の仕入税額控除を使用できる場合には、受領側に実質的な税負担はなく税収の観点からもニュートアルであるため、CBICとしてもコンプライアンス負荷の軽減の観点を重視し、納税者が請求書を発行しないで済むよう配慮した通達内容であると考えられます。
執筆・監修

|
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |

|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |