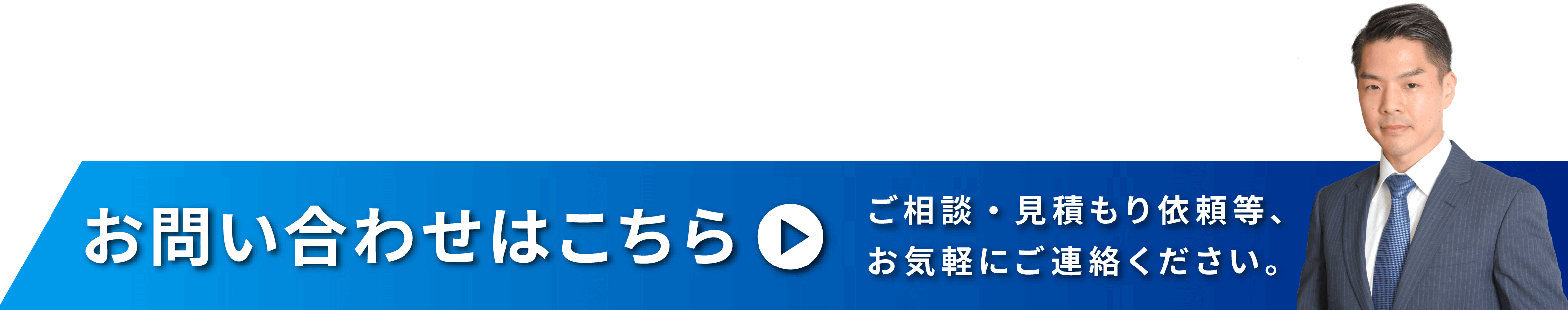急速なデジタルエコノミーの発展により、旧来型の国際課税制度では適切な所得課税や各国への税配分が達成できない事例が多くあります。Google、Facebook、Amazonなどの多国籍企業の提供する電子商取引は従前のビジネスモデルと異なり市場国に支店や工場を持たずにサービスを提供することが可能です。旧来型の国際課税制度では支店や工場を恒久的施設(Permanent Establishment - PE)と認定した上で、PEを起点に市場国で課税してきました。しかし、Google、Facebook、Amazonなどの多国籍企業は市場国にPEを保有することなく電子商取引を提供可能なため、これらの巨大IT企業に対して市場国でいかに源泉地国課税を行っていくかが争点となっています。
電子商取引に対する課税に関して、多くの巨大IT企業を抱える米国が居住地国課税(=巨大IT企業の居住する国で課税する考え方)を主張する一方で、ヨーロッパを中心とする市場を抱える国が源泉地国課税(=サービスの消費地で課税する考え方)を主張している構造が見られます。この国際課税問題に対応するためOECDとG20諸国が協議を進めていますが、インド政府もインド独自のデジタル課税制度の導入と運用をしています。
目次
全世界的な協議の流れ
国際間の税制の隙間や抜け穴を利用した税源浸食や利益移転(Base Erosion and Profit Shifting - BEPS)による租税回避へ対抗するために、OECDとG20諸国が協力して2015年11月にBEPS行動計画に関する最終パッケージを公表しました。最終パッケージでは15つの行動計画が示されており、そのうち行動計画1は「 デジタル経済での課税上の課題への取組み(Action1: Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy)」です。これは、電子商取引により他国から遠隔で販売、サービス提供等の経済活動ができることに鑑み、電子商取引に対する直接税・間接税の在り方を検討することを目的とした取組みです。行動計画1では、電子商取引に対して下記3つの税制オプションが示されておりました。
- 重要な経済的存在(Significant Economic Presence - SEP)
- 源泉徴収税(Withholding Tax)
- 平衡税(Equalization Levy)
その後さらなる協議が継続して行われ2020年1月31日にデジタル課税に関する2つの柱からのアプローチについて大枠合意に達しました。これがBEPS2.0と呼ばれる取組みです。
- 第1の柱(Pillar1):市場国に対する一定の利益配分を目指す取組み
- 第2の柱(Pillar2):多国籍企業に対して最低税率の導入を目指す取組み
しかし、第1の柱に関しては課税事業者を抱える国(主に米国)とヨーロッパを中心とする市場を抱える国のせめぎ合いにより、当初の予定よりスケジュールが後ろ倒しになっている状況です。そのような状況下でインドをはじめとする一部の国では、独自のデジタル課税制度の導入及び運用が開始されています。
インド独自の取り組み
これまでのインドは国際会議での国際課税ルールの策定の場において、開発途上国(≒資本輸入国)の代表として源泉地国課税(=サービスの消費地で課税する考え方)を重視する立場を取ってきました。開発途上国は、源泉地国課税を適用することで自国の国民が使用するGoogle、Facebook、Amazonなどのサービスに対して自国内でこれらの巨大IT企業に対して課税することができるからです。
一方で、インドは国内に優れたIT関連産業を抱えている背景もありインド系IT企業が今の米国系IT企業のように今後世界でより活躍していくことを鑑みた場合、インドとしては居住地国課税(=巨大IT企業の居住する国で課税する考え方)の考え方も軽視することはできません。インドは多くの巨大IT企業の源泉地国であると同時に居住国にもなりえるため、デジタル課税に関する国際課税ルールの策定の場でインドがどのような役割を果たしていくのかは全世界が注目しています。
インド政府は国内法である1961年インド所得税法(Income-Tax, 1961)の修正または財政法(Finance Acts)を通して「①PE概念の拡大」及び「②平衡税(Equalization Levy)の導入」の観点から、デジタル課税に対応しています。以下ではインド所得税法及び2016年財政法での電子商取引に対する国際課税ルールを見ていきます。なお、インド所得税法の規定を検討する際は、併せて租税条約での規定を確認することも重要となるためご注意ください。
①PE概念の拡大
インド所得税法第9条は事業所得を課税する要件として、PEの概念の代わりに事業関連性(Business Connection)という概念を用いています。事業関連性の概念はOECDモデル条約のPE概念より広い概念となっています。デジタルエコノミーの文脈で考えると、多国籍企業の運営するWebサイト自体はOECDモデル条約のコメンタリーではPEを構成しないと解釈されている一方で、インド所得税法ではWebサイト自体も事業関連性の根拠となると整理されます。背景には非居住法人が自ら管理する物理的拠点なしにWebサイトのみを通じて事業をする場合の事業所得に関して、インド所得税法の下でも可能な限り課税できるようにしたいというインド政府の考え方があるように見受けられます。
また2018年には、重要な経済的存在(Significant Economic Presence - SEP)という概念がインド所得税法に導入されました。非居住者法人がインド国内にSEPを有する場合には、その非居住者法人はインド国内での事業関連性があるものとみなされ、事業所得に課税されることになります。
上述のBEPS行動計画1の示した税制オプションの内、1つ目の重要な経済的存在(Significant Economic Presence - SEP)の考え方が、インド政府が進める電子商取引に対する国際課税ルールの基本路線と考えられます。従来のPEに加えてSEPという新たな課税根拠(ネクサス)を国際的に導入すべきという立場です。
しかし、巨大IT企業の電子商取に対してSEPを根拠に事業所得として課税する方法には、国際的な合意が取れていない現時点では下記のような限界があります。
- インド所得税当局が納税者との裁判で必ず勝訴できるわけでない(実際に過去には納税者有利の判定が出ているケースも多くあります)
- SEPを根拠としてインド所得税当局が行う積極的な課税姿勢は、非居住者法人にとってインドビジネスの法的安定性や予見可能性を損ないかねず、外国投資の誘致の促進の観点から難点がある
②平衡税(Equalization Levy)の導入
インドは2016年6月に世界に先駆けてデジタル広告課税として平衡税(Equalization Levy)を導入しました。これは、BEPS行動計画1が示した税制オプションの3つ目に対応する方法です。BEPS行動計画に関する最終パッケージが公表されたのが2015年11月であることを鑑みると、BEPSの議論の直後に導入されたことが分かります。この背景には、インド企業と多国籍IT企業との間の税負担の非対称性はインド国内市場における競争に歪曲的な影響を与えるため、本非対称性を直ちに是正したいというインド政府の意図が見て取れます。
平衡税(Equalization Levy)の設計及び導入に当たっては、財務省のAkhilesh Ranjan氏を座長とし財務省職員や税理士など8名から構成される、直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes - CBDT)の諮問委員会である電子商取引税制委員会(Committee on Taxation of E-Commerce)が組成されました。電子商取引税制委員会はBEPS行動計画1の示した3つの税制オプションをそれぞれ検討した上で、その3つ中から最適案として平衡税(Equalization Levy)を勧告しました。これを受けインド財務大臣は、2016年2月29日に予算案の一部として平衡税(Equalization Levy)を導入することを発表し、2016年6月1日の取引から平衡税(Equalization Levy)の徴収が開始されました。ただ、平衡税(Equalization Levy)の導入に当たっては所得税法の改正による導入ではなく、2016年財政法での導入となりました。これは、ネット所得に対して課税する法人所得税とは別の税として平衡税を位置づけ、平衡税の課税に租税条約の制約を及ばせない意図があると考えられます。平衡税は、言わば租税条約を敢えて無視した、インド政府の一方的な課税措置であると言えます。なお、平衡税の課税対象となった支払いについては、インド所得税法ではその支払い受領者の所得には含まれず、インドでの所得税申告も不要です(インド所得税法第10条50項)。
導入当初は、平衡税(Equalization Levy)の課税対象はデジタル広告事業に限定されていました。これには平衡税(Equalization Levy)を源泉徴収の形態で徴収したいインド政府の意図があり、課税対象をBtoB取引に限定せざるを得なかったものと考えられます。つまり、源泉徴収の形態で税金を徴収する場合には、デジタル広告事業を営む非居住法人が直接インド所得税当局に平衡税(Equalization Levy)を納税する必要はなく、インド居住法人が当該非居住法人にデジタル広告サービスの対価を支払う際に天引きする形で徴収されます。よって所得税当局の執行管轄権の及ばない非居住法人に対しても平衡税(Equalization Levy)の徴収を確実なものとすることが可能になります。
また、2016年財政法第165条2項a号ではデジタル広告事業者が、インド国内にPEを有しデジタル広告サービスが当該PEと関連性がある場合(=デジタル広告サービスがインド国内で事業所得として課税されている場合)には平衡税(Equalization Levy)の課税対象とはならないと規定しています。平衡税(Equalization Levy)はインドに拠点を持たない非居住者法人を狙い撃ちした狙いが、ここから見て取れ平衡税(Equalization Levy)は最大の税負担者の名をとって「グーグル税」という俗称でインド国内では呼ばれました。
その後、2020年4月から電子商取引も平衡税(Equalization Levy)の課税対象に加えられ(インド所得税法第165A条)、2023年10月時点でインドの平衡税(Equalization Levy)の対象となる取引はデジタル広告(Online Advertisement Services)と電子商取引(E-commerce Supply)の2種類です。
なお、平衡税(Equalization Levy)はあくまでも暫定的措置であり、インド政府の電子商取引に対する国際課税ルールの基本路線としては上述の「重要な経済的存在」を軸に対処していくものと考えられておりました。そして、2024年度財政法では電子商取引に係る平衡税が2024年8月以降の廃止が発表され、2025年度財政法ではデジタル広告に係る平衡税が2025年4月以降の廃止が発表されています。
参考文献:上田衛門(2020)「経済・社会のデジタル化とインドの税制―国際課税問題への対応を中心に」『フィナンシャル・レビュー / 財務省財務総合政策研究所 編』
執筆・監修

|
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |

|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |