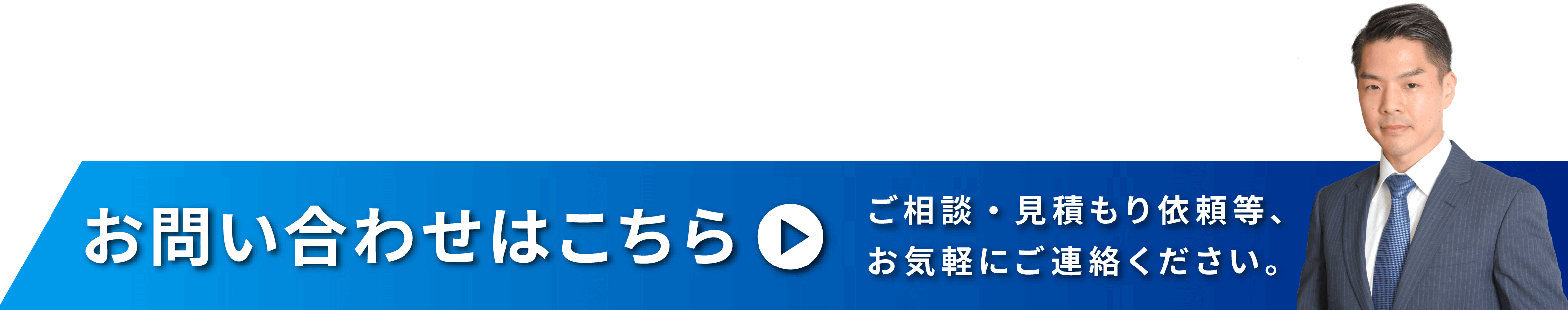インドは世界でも駐在コストが最も高い国の一つであり、その要因の一つが日印での社会保障費の二重負担でした。特に従業員数・駐在員数の多い企業にとっては相当の負担で、その負担を軽減するべく早期の社会保障協定が望まれていました。そして2012年に協定が署名されまもなく発効かと期待が高まったがインド側の社会保障制度の改正などがあり一旦その手続きが止まってしまいました。最終的に2016年10月1日に無事に日印社会保障協定が発行し、現在はその運用が始まっています。ここでは、インド側の社会保障制度に関する説明は割愛しますが、運用するにあたって理解しておくべき5つのポイントについて以下の通り整理しました。
1. 概要
- 発効日 2016年10月1日
- 対象となる社会保障制度
両国の年金制度のみが対象となる。
◆日本 :国民年金・厚生年金保険
◆インド :被用者年金(EPS)・被用者積立基金(EPF)等
※インド側で等とあるのは、被用者預託金連動型保険(EDLI)・事務手数料は年金ではない ため協定の適用対象外であるがインド国内法上一体運用されているので、原則EPS・EPFと同一の取り扱いを受ける。 - 申請書の代理受理
日本で以下のインド年金の申請が可能となる。
- 被用者年金制度(Employees’ Pension Scheme-EPS)
- 被用者積立基金制度(Employees’ Provident Fund-EPF)
2. 二重負担の解消
- 適用調整のルール
派遣先国(日本からの派遣の場合にはインドの制度)のみに加入することが原則となる。
⇒ 一定条件(派遣期間が5年を超えない)を満たす場合には例外的に派遣元国の制度のみへの加入が可能となる。 - 適用調整の対象となる派遣期間の延長
派遣期間を延長して合計が5年を超えるようにすることは、予見できない特段の事情等がある場合に、個別に両国間で協議し、合意した場合に認められる。
⇒ 形式的に日本年金当局が打診し、インドEPFOが合意することになるが合意することが暗黙の了解事項となっている。ただし、延長期間は3年を超えない期間とされている。
当初の派遣期間と延長期間の合計が8年(5年+3年)を超える場合であっても、派遣者の収入が一定基準を超えるためにインドの被用者年金制度(EPS)に加入することができない場合(2014年9月施行のインド年金制度改正により、月収1万5千ルピーを超える外国人労働者等はインドのEPSに加入不可)は、日本制度に継続して加入することができる。
⇒インドの年金当局と2014年9月の改正を鑑み、延長期間は最大で3年とされているが、その例外として月収1万5千ルピーを超える日本人労働者については、さらに個別で両国間で協議し、合意した場合に期間の延長が認められることとなっている。 - 協定発効前から派遣されている派遣者について
当該発行日を起算点として、予定された派遣の期間が5年以下と見込まれる場合には、インドの制度への加入が免除される。つまり、協定発効前の派遣期間は通算されない。 - 随伴する配偶者・子
日本からインドに派遣された被用者に随伴する配偶者については、日本の年金制度が引き続き適用される。インドで就労しない限り、インド年金制度の適用はない。
3. 保険期間の通算
年金の受給資格要件を満たすため、相手国の年金保険期間を算入することができる。
- 日本の老齢年金では、現在、25年の年金保険期間が必要だが、日本の期間だけでは25年を満たさない場合、日本の期間と重複しない限りにおいてインドEPSの保険期間を足し合わせて計算できる。
- インドEPSにおける老齢給付では、現在10年の年金保険期間が必要だが、インドの期間だけで10年を満たさない場合、インドの期間と重複しない限りにおいて日本の年金保険期間を足し合わせて計算することができる。
=> 両国の年金保険期間で重複した期間はダブルカウントしない。
4. 適用証明(Certificate of Coverage - COC)の取得方法
インド年金制度の適用免除を受けるには、派遣前に日本において「適用証明書」の発給を受ける必要がある。
- 日本の事業主から年金事務所へ適用証明書交付申請書を提出
(申請書入手先:http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.files/1.pdf)
⇒通常は2週間程度で発行可能
※延長の場合には適用証明期間継続・延長申請書
(延長申請書入手先:http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.files/5.pdf)
⇒延長の場合の申請は5年の期間を過ぎる前から申請を行う。おおよそ3~6ヶ月前から申請を受け付ける。 - 一時派遣者に対して適用証明書を交付(見本:http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/0826-02.files/7.pdf
- 一時派遣者からインドの勤務先へ提出
- インドEPFO(被用者積立基金機構)から提示を求められた場合に、適宜提示
5. 協定発効前から派遣されている派遣者の適用証明の取得
- 日本の事業主から適任事務所に対して適用証明書の交付申請する。
⇒申請書の就労開始日は、協定発効日である2016年10月1日として申請 - インド側でEPFOに対してインド制度からの脱退手続きを行う。
⇒手続きの際に日本側で取得した適用証明書が必要
⇒手続き方法はインド側の当局の手続きに準じる。
執筆・監修

|
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |

|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |