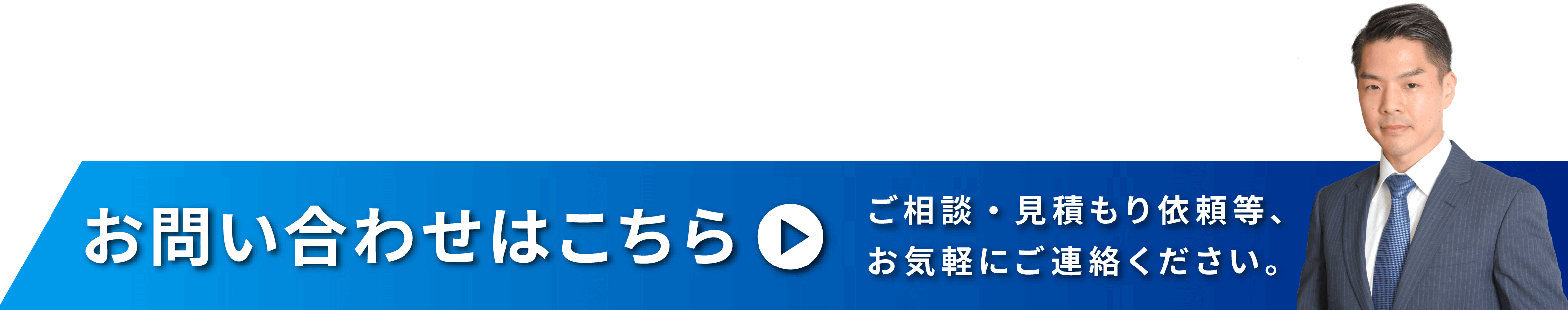インド国内法人がインド会社法第 248 条の規定する登記抹消(Striking Off)を行う際には、一連の登記抹消手続には残余財産の分配という考え方がないため、登記抹消手続きを開始前に以下の①~③のいずれかの方法で残余財産の資金還流を行う必要があります。
税務負担効率、還流金額の上限および実行までのコンプライアンス負荷を考慮した上で最適な資金還流方法を検討することが求められます。
| ①配当 | ②自己株式の取得 | ③減資 | |
| 会社側の課税 | なし | なし | なし |
| 株主側の課税 |
|
みなし配当
|
みなし配当
キャピタルゲイン
|
| 還流上限 | あり | あり | NCLTの承認が必要であるが基本的に上限はなし |
| 実行承認 | 取締役会/株主総会での承認 | 取締役会/株主総会での承認 | 取締役会及び株主総会での承認かつNCLTの承認 |
①配当
インド所得税法第115A条は非居住者が受け取る配当に対する所得税率を20%(+加算税、教育目的税)と規定しています。一方で日印租税条約第10条2項では、配当を受ける法人は支払国で10%を上限に課税できると規定しており、この日印租税条約の規定はインド所得税法に優先して適用されます(インド所得税法第90条)。
また配当を支払うインド法人は支払い時に源泉徴収税(Tax Deducted at Sources - TDS)を源泉徴収する必要があり、日印租税条約を適用しない場合のTDSは20%(インド所得税法第195条、財政法)、適用する場合のTDSは10%となります。
なお従来インド内国法人が配当支払い時に負担していた配当税(Dividend Distribution Tax-DDT)は2020年度国家予算にて撤廃されました。よって、配当は配当所得として株主側のみで課税されます。
②自己株の取得
自己株式の取得時に買戻しを行う法人側に課せられていた株式買戻税(Buy Back Tax - BBT)は2024年10月以降廃止となり、自己株の買戻しを行う会社側ではなく、株主側でみなし配当として課税されるようになっています(インド所得税法第2条22項f号、第194条、インド所得税法第10条34A項但し書き)。これは、別の株主への資金還流方法である配当と課税関係の整合を取る形で法改正となります。
③減資
上述の「①配当」及び「②自己株の取得」は取締役会や株主総会での決議で実行が可能ですが、減資の実行には会社法審判所(NCLT)の承認が必要であり(インド会社法第66条)、一定の時間及びコストがかかります。そのため、一般的に減資は十分な累積利益が無い状態の会社が自己株取得の上限額を超えて資金還流を希望する場合等に採用される方法になります。
減資を通して株主に支払われる払戻額のうち累積利益額まではみなし配当となります(インド所得税法第2条22項d号)。配当に関して発生する所得税は、「①配当」と同様になります。一方でみなし配当に関する課税に対しては、租税条約を適用できないという意見もあり最終的なポジションは慎重に検討する必要があります。
キャピタルゲインに発生する所得税
次にキャピタルゲインについてです。株式取得金額と資本金相当額(減資を通して株主が受け取った額からみなし配当額を差し引いた額)の差額がある場合にその差額が、キャピタルゲインとなるか(インド所得税法第46条)は争点となっていました。つまり、減資による株式の消滅はインド所得税法第45条1項の定めるキャピタルゲインの定義の資本財の「Transfer」に該当するかが論点でしたが、減資による株式の消滅も「Transfer」に該当しキャピタルゲインが発生するという最高裁の判決が出ています(The Hon’ble Supreme Court / Kartikeya v. Sarabhai v. CIT: 228 ITR 163)。
所得税率は短期キャピタルゲインと長期キャピタルゲインでそれぞれ規定されており、長短分類は下記に従います(同法第2条29AA項、42A項)。
| 資産の区分 | 保有期間 |
| 長期キャピタルゲイン | 24か月超 |
| 短期キャピタルゲイン | 24か月以内 |
長短分類ごとの税率は下記の通りです(同法第条112条1項c号iii、財政法)。
| 資産の区分 | 税率 |
| 長期キャピタルゲイン | 12.5%(+加算税、健康教育目的税)で課税 |
| 短期キャピタルゲイン | 35%(+加算税、健康教育目的税)で課税 |
なお、上記の表は清算対象の会社がインド国内の非上場会社であり、株主はインド非居住者である前提です。
執筆・監修

|
鈴木 慎太郎 | Shintaro Suzuki |

|
新井 辰和 | Tatsuo Arai |